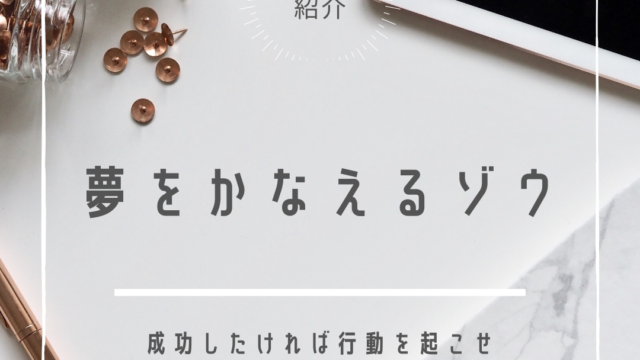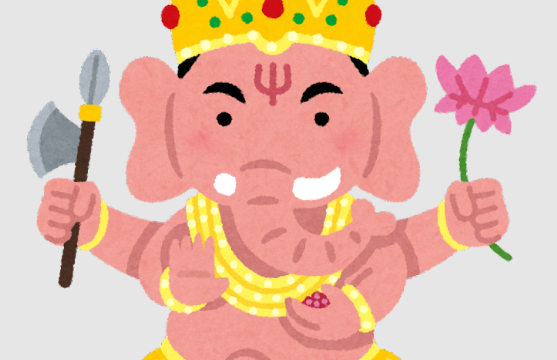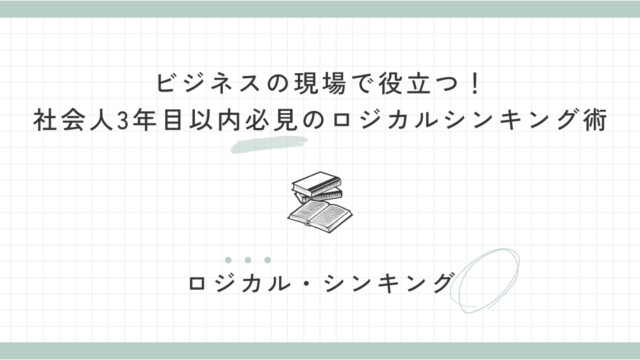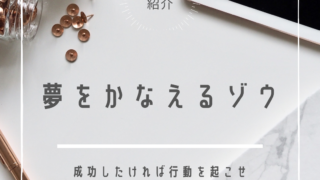こんにちは。らくらく学び舎のれっとです。
語学・資格の勉強や読書、専門スキルの習得など、自信のスキルアップを図るために新しい取り組みに挑戦したものの、3日と続かず、あの時のメラメラとした情熱は何処へやら・・・そんな経験はありませんか?
始めるときはあれほどモチベーションが高かったはずなのに、なぜ今も続けられていないのでしょうか。
それは決して、熱意が足りないわけでも、努力が足りないわけでもありません。
足りなかったもの、それは「習慣化の方法」を知らなかったことです。
習慣は次の3STEPで誰でも・いつからでも簡単に作れる
1.脳を騙す
2.仕組みを作る
3.ハードルを下げる
この記事では著書「習慣が10割」について、重要なポイントだけにフォーカスしてご紹介します。
「習慣が10割」は習慣形成コンサルタントとして、ビジネスマンや学生など5万人以上に習慣の作り方を教えた著者が、そのノウハウをまとめた一冊です。
私自身、この本を読んだことで、それまで苦手だった習慣化が簡単にできるようになり、英語学習・読書・ボディメイキング等、いくつもの習慣が全くストレスなく1年以上続いています。
この記事では、そんな私が学んだ「習慣化のコツ」をお伝えしたいと思います。
いまアナタができることは、まぎれもなく過去の習慣によって得られたものです。
振り返ってみてください、どれも最初からできたわけではなく、少なからず努力していますよね?
つまり、アナタが描く「なりたい自分」を作るのは、未来の習慣に他なりません。
さぁ今ここが、理想の未来への第一歩です。
習慣とは
習慣化の方法を知る前に、まずは準備が必要です。
ただやみくもに方法論だけ知ったとしても、何のために習慣を作りたいのかが明確でなければ、無駄な努力に終わってしまいます。
この章では、まず習慣とは何か、そして習慣化の前に大事なゴールとスタートの設定からお伝えしていきます。
習慣とは
そもそも「習慣」とは何を指し示すのか、ChatGPTで調べてみました。
ラテン語の「habitus(状態、習慣)」に由来し、個人や社会が文化的・社会的な規範に沿って行動するための自動化された反応として定義されます。
「自動化された反応」ということは、意識せず・何気なくやってしまうことが「習慣」と言えるでしょう。
例えば、ご飯は3食取るとか、食後に歯を磨くとか、夜はお風呂に入るなども、立派なアナタの習慣です。
栄養失調ではないことも、虫歯だらけではないことも、清潔であることも、まさに習慣の力によるもので、すなわち今のアナタを形成しているのは過去の習慣なのです。
目標を具体的に描く
ここからは習慣化に取り組む前に必要な目標の設定と現在地の理解について学んでいきましょう。
「習慣」は思いの深さ×反復によって成り立ちます。
では、どうすれば思いを深めることができるのでしょうか。
それは目標、すなわち「なりたい自分」を具体的に描くことです。
なぜ目標を具体的に描くことが良いか、それは人間の脳にあるメカニズムが作用するからです。
左脳は過去を、右脳は未来を司っていますが、人間は過去の経験を活かせるようにできているため、左脳がより強い影響を持ちます。
そのため、未来のイメージを強く・鮮明にしていなければ、左脳の「習慣化できなかった」過去に支配されてしまうのです。
更に目標は家族や友人など、周りの人に宣言するとさらに効果を発揮します。
それは人間のもつ「一貫性の原理」を刺激することができるからです。
「一貫性の原理」とは、発言と行動を一致させたいという人間の自動的な行動パターンのことです。
つまり、周りの人に宣言したことは、本能的に達成させたいという思いが深くなるのです。
現在地を知る
目標を描いたら、次に必要なのは現在地、すなわち今の自分を知ることです。
それは何故か、ゴールがわかっていてもスタート地点がわからなければ、どの方向に向かえば良いか、つまりどんな努力をすれば良いかが見えてこないですよね。
では自分を知るためには何をすれば良いか、その方法は2つあります。
まず1つめは、自分の好きなところ(長所・特技・大事にしていることなど)や嫌いなところ(直したいところ・苦手なもの・誰かに私的された短所など)を書き出すことです。
この方法で大切なことは、誰かに発表するものではないので恥ずかしがらず、飾らずに素直に思ったことを書き出すことです。
次に2つめは、周りの人に「自分がどんな人であるか」を質問することです。
この方法の良いところは、自分では気付けなかった本性を知ることができることろです。
もちろん良い面・悪い面あると思いますが、自分にどのような習慣があるのかを知ることはとても重要です。
STEP1:脳を騙す
何故、脳を騙す必要があるのか、これも人間の本能的なプログラムが関係しています。
それは、心地よい・楽しいなどの快楽に近づく「接近本能」と、苦しい・辛いなどの不快を避ける「回避本能」です。
つまり、習慣化したいことを快楽と思えるようになることができれば、本能的にその行動に接近し、いつの間にか習慣化ができるということです。
では、具体的にどうやって脳を騙すことができるか、その方法にも脳のメカニズムを利用します。
どのようなメカニズムかと言うと、脳はInputよりOutputを信じるというものです。
ここからは脳を騙す方法として、1.言葉で騙す、2.行動で騙す、3.思い込みで騙す、を学んでいきましょう。
言葉で騙す
まず1つめの「脳を騙す」方法は、とにかくポジティブワードを口に出すことです。
気を付けていただきたいのは、「思う」だけではなく「口に出す」ことが大切です。
例えば、「今日も3ページ本を読めた、継続できて偉いぞ!」とか、「TOEICの問題を5問解いた、成長できたぞ!」など、成果の大小は考えず、とにかく今日できたことを前向きな言葉で口に出しましょう。
行動で騙す
次に2つ目の「脳を騙す」方法は、習慣化したいことをできたときに何かポーズをすることです。
つまり、例えば読書を習慣化したい場合は、本を読んだ後にポーズをとるのです。
どのようなポーズをとるか、空を見上げてガッツポーズをするが特におススメです。。
上をみること・ガッツポーズをすることは、自信をつけたり、幸福感や肯定感を高めるという研究結果がいくつもあるそうです。
更にポジティブワードを口に出しながらポーズをとると、相乗効果が生まれるでしょう。
思い込みで騙す
「とは言え、小さな成果で喜ぶなんて恥ずかしい」、「なかなかポジティブに考えられないよ」という方に実践いただきたいのがこの方法です。
具体的には、日常で当たり前と思っているようなことを、「〇〇でよかった」と書き出すことです。
例えば、「今日も良い天気で気持ちよかった」とか、「今日もネットが繋がってよかった」、「今日もご飯が食べられてよかった」と紙に書いたり、スマホにメモしたり目に見える形でOutputしてください。
ご紹介した3つの脳を騙す方法は、どれも簡単にできるものだったと思います。
「それって本当なの?」と疑っているかもしれませんが、とにかく実践してみてください。
この章の冒頭でお伝えしたとおり、人間の脳はOutputを信じるように設計されています。
STEP2:仕組みを作る
この章でまず理解していただきたいことは、人間の意志はとても弱いということです。
いつだって楽をしたいし、大変なことは避けたい生き物なのです。
では、どうすれば意志に頼らなくて済むのか、それは仕組みを作って自動化することです。
ここからは自動化の具体的な方法として、1.時間・場所を決める、2.トリガーを決める、3.他人を巻き込む、を学んでいきましょう。
時間・場所を決める
習慣化を始めるとき、「毎日15分やる」というように頻度・長さを決めるだけでは、15分をいつ始めるかは意志に依存してしまいます。
つまり、「いつ始めるか」を固定することで、自動化ができるというわけです。
では、どのように固定するか、1つ目は時間や場所を決めることです。
例えば、朝の通勤電車で〇〇駅から××駅まで、昼休みの終了15分前など、具体的に決めましょう。
トリガーを決める
自動化のもう1つの方法として、トリガーを決めるというものがあります。
つまり、既存の習慣に組み込んで自動化するという方法です。
例えば、朝のコーヒーを飲みながら、食後の歯磨きが終わったらなど、これも具体的に決めましょう。
この方法のメリットは、既にある習慣に付け足すだけなので、習慣化そのものが自動化されます。
他人を巻き込む
第1章で、目標を宣言することで「一貫性の原理」が作用することを学びましたが、仕組み作りにも宣言の効果は絶大です。
習慣化したいことをSNSに投稿したり、友人や家族に話すことで宣言しましょう。
単にやることを宣言するだけではなく、例えば読んだ本の感想を伝えるなど、結果を発信することで更に一貫性が高まります。
他人を巻き込むことは、「一貫性の原理」を作用させるだけではなく、誰かの反応を得られるメリットもあります。
例えば、応援の声でモチベーションがあがったり、取り組みを改善するアイデアを聞くこともできますよね。
この章では習慣化の仕組み作りを学びました。
習慣化を船に例えるならば、エンジン(=意志)を強力にしても、いつかはガソリンが費えて船は動かなくなってしまいます。
風を利用して進む帆船のように、周りの環境を上手に活用しましょう。
STEP3:ハードルを下げる
習慣を作り出す最後のSTEPとして、私が最強のテクニックだと思う「ハードルを下げる」をご紹介します。
なぜ最強なのか、それは習慣を始めた人の多くが最初の熱意で高い目標を設定し、挫折してしまうからです。
もちろん、なりたい自分として高い目標を設定することは良いことです。
しかし、習慣化に慣れてもいない人が高い習慣目標を設定することは、習慣化に失敗するリスクを高めてしまうだけです。
では、具体的にどうやってハードルを下げるのか。
アプローチは2つ、「何を」の部分を下げる「小さな習慣から」、「どこまで」の部分を下げる「合格ラインを下げる」です。
習慣が身に付かない人は、まず2つを組み合わせて、習慣化に慣れることから始めましょう。
小さな習慣から
まだ習慣化に慣れていない人は、試験勉強や読書など本当に習慣化したいことから始めないでください。
まずは「家に帰ったら靴を揃える」とか、「食事の後はテーブルを拭く」など、とにかく絶対にできる簡単なことから始めましょう。
「そんなことでいいの?」と思うかもしれません、むしろそう思えるようであれば良い傾向です。
小さな習慣から始める重要なポイントは、「自分で決めたことを習慣化した」という実績を作ることなのですから。
人間が何かに自信をもつことができるのは、それを成し遂げたという実績に他なりません。
つまり、小さなことから実績を作って、自分は習慣化ができる人間なんだという自信を得ましょう。
合格ラインを下げる
どんなことを習慣化する上でも必ず必要なこと、それは達成量・継続期間の合格ラインを下げることです。
例えば、読書を毎日30分する習慣を作りたいと思った時、始めから毎日30分できなくてもいいのです。
序盤のうちは5分でも、本を開いただけでも「合格」にしましょう。
継続期間についても同様で、仮に3日坊主になってしまっても、3日続いた自分を褒めましょう。
また明日から再開すれば良いのです。
最後に習慣化を成功させる秘訣をお伝えします、それは「習慣化を辞めない」ことです。
まとめ
まず、改めて習慣を作る3つのSTEPを整理します。
1.脳を騙す
2.仕組みを作る
3.ハードルを下げる
この記事では、習慣化の前にすべきこと、上記3STEPの具体的な方法について学んできました。
振り返ってみると、習慣化はそのコツさえ知ってしまえば、難しくないことがわかったと思います。
「今日が人生で一番若い日」です。
習慣化の3STEPを上手に活用して、習慣化のプロになりましょう!