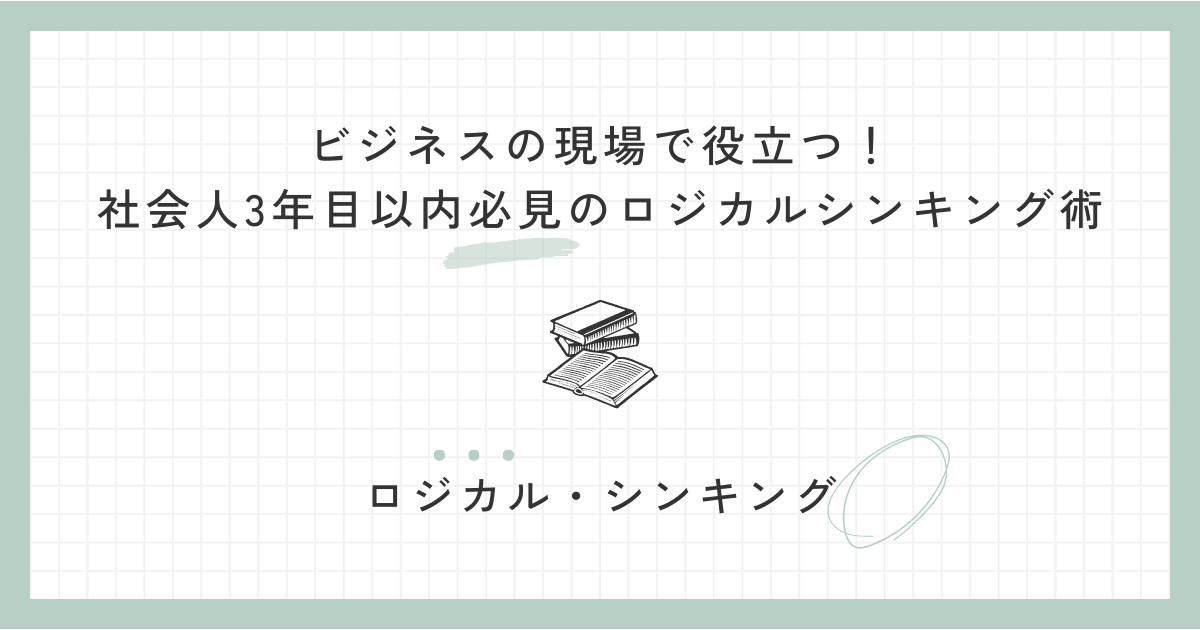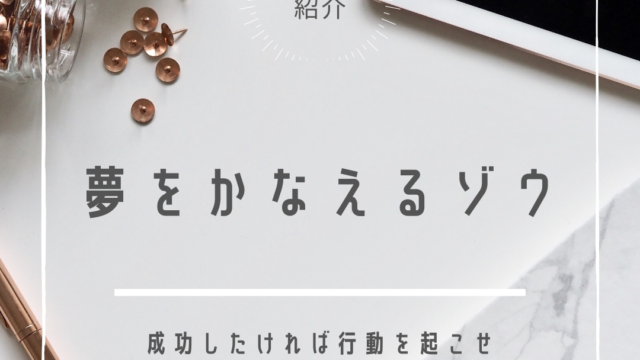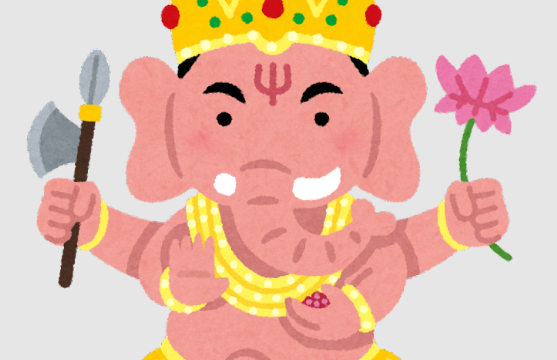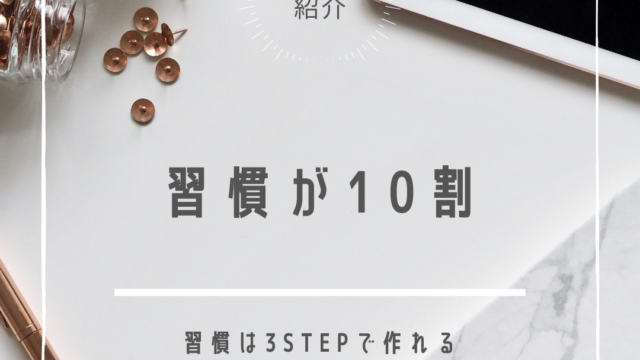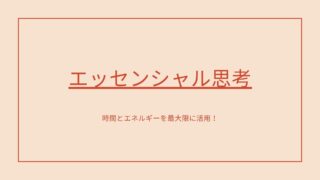ロジカル・シンキングは、ビジネスシーンで重要なスキルとされています。
しかし、具体的にどういうことなのか、どのように身につけることができるのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
この記事では、社会人3年目以内の方にとって必読である「ロジカル・シンキング」の解説を通して、ロジカル・シンキングの基本的な考え方をご紹介します。
それでは、まず結論です。
ロジカル・シンキングとは、以下のメソッドを用いて情報を整理し、原因や結果、関係性などを考え、正確な結論を導き出すこと
1.MECE
2.So what/Why so
「ロジカル・シンキング」という著書は、超一流の経営コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーで、コミュニケーション・スペシャリストとして活躍した著者が、論理的思考の方法をまとめた一冊です。
私も現在、某コンサルティングファームに勤務していますが、入社時にはこの本を読んで、それまで感覚的だった論理的思考を、言語として理解して身に付けることができました。
ロジカル・シンキングを身に付けることで、情報整理がしやすくなり、問題解決や意思決定がスムーズになります。また、プレゼンテーションや報告がわかりやすくなるため、コミュニケーション能力が向上し、キャリアアップにもつながります。
相手に伝えることは何か
ビジネスの場では、上司やクライアントへの報告、営業での提案など、様々なコミュニケーションが必要になります。相手に伝えるべきメッセージとは、あなたが話したいことではなく、①課題、②答え、そして③期待する反応です。
①課題とは、何について議論をしたいかを明確にすることです。相手と課題認識が一致していなければ、議論は進みません。
②答えは、メッセージの中心となる部分です。結論と根拠から構成され、アクションの場合は方法が加わります。根拠から論理的に答えを導くことが重要です。
この「根拠から論理的に答えを導く」方法について、後続の章で解説していきます。
③期待する反応は、コミュニケーションのゴールです。理解、フィードバック、行動のいずれかを期待し、始めに整理することが大切です。相手にとって聴きやすく伝えることが、相手の反応を引き出すポイントです。
なぜ説得力がないのか
説得力のある話をするためには、論理的な構成が必要不可欠です。
一方で、論理的でない話にはどのような特徴があるのでしょうか。
まずは、その特徴について考えてみましょう。
まず、話に漏れやずれがある場合です。
例えば、部下に「日本国内における飲料にはどのようなものがあるか報告して欲しい」と依頼したとします。
そのとき部下が、「ビール、コーラ、烏龍茶・・・」と始めから具体的な種類を列挙したとしましょう。
それを最後まで聞いたとき、「確かにすべて報告したくれた」と思えるでしょうか。
次に、論理に飛躍がある場合です。
例えば、Aさんが「パンダ社の笹緑茶は、日本における売上高が1番の緑茶です。つまり、日本で最も売れているお茶です。」と言ったとします。
しかし、緑茶以外にも日本茶や紅茶、烏龍茶など、お茶には多様な種類があります。
また、緑茶市場が小さい可能性もあり、紅茶の中には笹緑茶よりも売上の高い商品があるかもしれません。
では、論理的な構成とするためには何をすれば良いのでしょうか。
以降の章で具体的に実践すべきことを学んでいきましょう。
重複・漏れ・ずれの防ぎ方~MECE~
話の重複や漏れ、ずれを防ぐ方法は、MECE(ミーシー)に分類することです。
MECE:MutuallyExclusiveCollectivelyExhaustive(相互に重なりなく、漏れなく)
MECEによって、全体集合とそれを構成する部分集合が示され、話がグッとわかりやすくなります。
例えば、移動手段にどのようなものがあるかを、MECEに分類・構造化すると以下のようになります。
・移動手段は公共交通、個別交通に分類される
・公共交通は陸上、海上、航空に分類される(個別交通も同様)
「移動手段は公共交通と個別交通に分類できます。また、それぞれ陸上・海上・航空に分類することができます。」
「公共かつ陸上の交通手段としては、電車やバスがあります。海上では定期船、航空では飛行機が考えられます。」
なお、MECEの分類は、4,5個以内に留めるのが理想的とされています。
あまりに多すぎると、聞いている方が覚えておくことが困難になります。
さらに、フレームワークを知っておくと、MECEをより使いこなせるようになります。
代表的なフレームワークには、3Cや4P、SWOTなどがあります。
どのようなフレームワークをいつ活用すると有効か、是非ご自分で調べてみてください。
論理の飛躍の防ぎ方~So what/Why so~
論理の飛躍を防ぐ方法は、So what/Why soで自分自身に対して質問をすることです。
So what(だから何?)とは、複数の要素から何が言えるのかを自問し、結論を導くことです。
一方、Why so(何故、そうなのか?)とは、結論に対してその根拠は?を自問し、根拠の確からしさを検証することです。
So what/Why soで繋がる関係となれば、論理の飛躍がない状態になります。
例えば、「日本の高齢化社会はますます加速する。」という結論に対して、根拠が「2021年時点で、日本の人口における65歳以上の割合が約3割であるため。」では、論理に飛躍があることはお分かりいただけると思います。
では、論理に飛躍のない結論と根拠とはどのようなものでしょうか。
先ほどと同じ結論の場合、どのような根拠があるでしょうか。
【根拠】
・2021年時点で、日本の人口における65歳以上の割合が28.9%で、1950年以降は上昇傾向にある
・一方、15歳未満の割合は11.8%で、1950年以降は下降傾向にある
・医療技術の向上による健康寿命の延命、1975年以降の少子化により、その傾向は今後も継続すると考えらる。
まとめ
この記事では、論理的な思考方法として以下の2つをご紹介しました。
1.MECE
2.So what/Why so
MECEとは、結論を導くための根拠(要件)を漏れなく、重複なくする方法、So what/Why soは、「だから何?」「何故、そうなのか?」を自問し、結論と根拠の間に飛躍を無くす方法でした。
どちらの方法も、一朝一夕で身に付くようなものではありません。
何度も繰り返し思考を重ね、自然と活用できるようになる必要があります。
「今日が人生で一番若い日」です。
MECEとSo what/Why soによって論理的な思考を身に付けましょう。